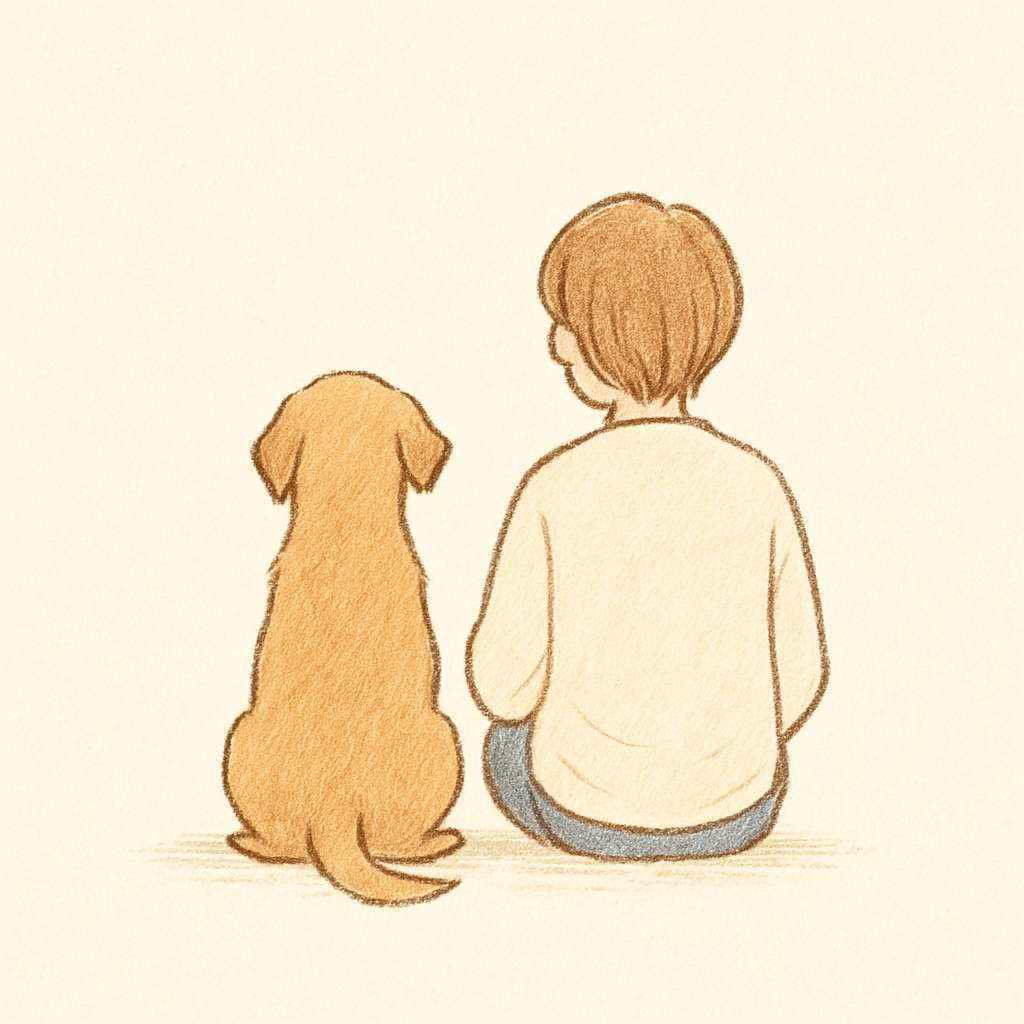はじめて迎える“うちの子”と、心地よい毎日をつくるために
「犬を飼ってみたいけど、ちゃんと育てられるかな?」
「近所に犬好きが多くて気になってきた」
「子どもにせがまれて、家族会議の議題にのぼった」
そんなきっかけで、犬との暮らしを考えはじめた方へ。
このコラムでは、今さら聞けない基本の「き」から、少し先を見すえたアドバイスまで、初めて犬と暮らす方に向けて、やさしくお話ししていきます。
「飼う」ではなく「暮らす」へ
まずお伝えしたいのは、「犬を飼う」という言葉にある“上から目線”をちょっと見直してみること。
犬はペットというより、もう「家族」です。最近では“うちの子”という表現も一般的になりました。
迎えたその日から、日々の暮らしを共にし、心配もし、時に涙し、そして無数の笑顔をくれる存在になります。
「かわいいから」だけでは続かないのが、犬との暮らし。
でも、「一緒にいられてよかった」と思える日々は、ちゃんと準備と心構えがあれば、誰にだって叶います。
【第一章】犬を迎える前に、考えておきたいこと
「犬と暮らす」と決めたとき、真っ先に思い浮かぶのは「どんな犬種にしようか?」というワクワクですよね。
でもちょっと待ってください。
犬は“ぬいぐるみ”ではありません。命ある存在であり、十数年もの付き合いになります。
だからこそ、「犬の種類を決める前に」考えておきたい、いくつかの現実があります。
■ 自分たちの「暮らし方」との相性チェック
まずは、家族のライフスタイルと、犬が快適に暮らせる環境がマッチしているかを見てみましょう。
✔ 家にいる時間は?
共働きで日中は不在、というご家庭では、留守番が得意な犬種や成犬の方が向いていることもあります。
逆に、常に誰かが家にいる環境なら、甘えん坊の犬や子犬でも安心して迎えられます。
✔ 住環境は?
集合住宅なのか、一戸建てなのか。
鳴き声が気になる? 散歩に出やすい立地? 床材は滑りにくいか?
こういった点が、犬種選びや生活スタイルに大きく影響します。
✔ 家族の理解と協力体制は?
「お世話は子どもがします!」という家庭、よく聞きますが、実際には大人の協力が不可欠です。
世話やしつけはもちろん、医療費の負担や旅行時の預け先など、家族全員で話し合っておくことが大切です。
■ 犬種の違いは“見た目”だけじゃない
柴犬、トイプードル、ゴールデンレトリバー…。
見た目の可愛さだけで選んでしまいがちですが、犬種ごとに「性格」「運動量」「しつけやすさ」「被毛のケアの手間」など、大きな違いがあります。
たとえば…
柴犬:日本犬らしく自立心が強く、気難しい一面も。吠えやすい傾向あり。
トイプードル:抜け毛が少なく賢いが、トリミング代がかかる。
ダックスフンド:好奇心旺盛でかわいいが、腰を痛めやすく、段差が多い家には不向き。
「この犬種が絶対に飼いやすい!」という正解はありません。
大切なのは、自分たちの暮らしとその犬種の特徴が合っているかです。
■ 子犬 or 成犬? 保護犬という選択肢も
犬を迎える=ペットショップやブリーダーから子犬を…という流れが一般的ですが、成犬から迎えるメリットもあります。
🐕 子犬の魅力
すべてが“はじめて”で、成長を一緒に見守れる
家族になじみやすい(社会化しやすい)
🐶 成犬の魅力
性格が安定している
トイレやお留守番などのしつけが入っている場合も
子犬よりも体調の変化に気づきやすい
特に最近は、保護犬を家族に迎える方も増えています。
「かわいそうだから」ではなく、「素敵な出会いの一つ」として、ぜひ保護犬譲渡会なども覗いてみてください。
■ 「犬がいる生活」をまずシミュレーションしてみよう
最後におすすめなのが、“犬がいる日常”を1週間、家族でシミュレーションしてみること。
- 朝晩の散歩、できる?
- 抜け毛やニオイ、気になる?
- フローリングや家具、大丈夫?
- お出かけの予定、どう変わる?
これをやるだけで、自分たちの覚悟や準備の足りなさ、逆に「これなら大丈夫かも」という安心感も見えてきます。
【第二章】犬と暮らす家の整え方
犬と暮らすということは、“人間だけの家”ではなくなる、ということ。
「犬のために家を変える」なんて大げさに聞こえるかもしれませんが、実はちょっとした工夫が犬の安心・安全・快適さをぐんと高めてくれます。
ここでは、住まいを犬目線で整えるための基本ポイントをご紹介します。
■ フローリングは“足の敵”?
多くの家庭で採用されているフローリング。見た目も掃除もしやすいのですが、犬にとっては注意が必要です。
犬の足裏には「肉球」がありますが、滑り止めにはならないため、フローリングの上ではツルツルと滑ってしまいます。
その結果、膝や股関節に大きな負担がかかり、特に子犬や老犬では脱臼やヘルニアの原因にもなりかねません。
対策アイデア:
- ペット用滑り止めワックス
- 滑りにくい床材(クッションフロア・ペット用フローリングなど)への張り替え
- 部分的にジョイントマットやカーペットを敷く(食事・寝床・通路など)
フローリング全部を張り替えるのは大がかりでも、リビングの一角だけでも改善できます。
■ 誤飲・誤食対策は「子育て」と同じ
犬は好奇心のかたまり。特に子犬期は、目についたものを何でも口に入れてしまいます。
人間の赤ちゃんと同じように、「口で世界を確かめている」ようなもの。
要注意なもの:
- コンセント・コード類(噛み癖のある子は特に危険!)
- ボタン電池・薬・人間の食べ物
- ゴミ箱(ふた付きタイプが◎)
- 床に置きっぱなしの靴下、子どものおもちゃ、観葉植物(毒性があるものも)
これらは、家中の“犬目線”での安全チェックが必要。
掃除と整理整頓が自然と習慣化される、という副次的効果もあります。
■ ケージやサークル=犬の“安心拠点”
ケージやサークルは、犬を閉じ込めるための道具ではありません。
むしろ、犬にとっては「誰にも邪魔されず落ち着ける場所」になる、とても大切な存在です。
特に、
- 留守番中
- 来客時や就寝時
- 災害時の避難(ケージ慣れしていないとストレス大!)
といった場面で、安全かつ安心できる空間として活躍します。
布で覆ってあげたり、お気に入りのタオルやクッションを入れたりすることで、“自分の巣”として心地よく感じるようになります。
■ ペット用ゲート、あると便利です
階段やキッチン、洗面所など、「ここは犬に入ってほしくない!」という場所には、ベビーゲートのような“ペット用ゲート”が便利。
子犬期のいたずら防止にも役立ちますし、料理中などの思わぬ事故も防げます。
取り付けタイプのものから、置くだけの簡易型まで幅広くあります。インテリアになじむ木製やアイアン製も人気です。
■ 実際は「うちはうち」になる
たとえば、玄関に勝手に出ないように、内側にスライド式の柵を取り付ける。
散歩の時にリードを付けている間など、一瞬のスキに外へ出てしまう事故を防ぐためです。
家の間取り的に階段の昇り降りが多かった場合、シニア犬になってからは滑り止めマット+柵で階段を封鎖。
リビングだけで快適に過ごせるよう、トイレや飲み水、くつろげる場所を集約する。
「犬のために家を変える」と考えると大変そうに聞こえるかもしれませんが、
「この子ともっと快適に暮らすために」と考えると、不思議と前向きになれるものです。
小さな変化が、大きな安心につながります。
【第三章】「しつけ」って、叱ること?
「ちゃんとしつけてね」
犬を迎えると、いろんな人に言われる言葉です。
でも、この“しつけ”って、具体的にどうすればいいのでしょうか?
そして「叱る」のが正解なのでしょうか?
結論から言えば、“しつけ”とは、犬が安心して暮らすためのルールを教えること。
決して、「人間にとって都合のいい犬にする」ことではありません。
■ 犬は“空気”より“結果”を覚える
まず大前提として、犬は「今の自分の行動が、どんな結果につながったか」を通して物事を覚えます。
たとえば、
- ごはんの前におすわり → 褒められる → ごはんがもらえる → 「おすわり=いいことがある」と覚える
- トイレを失敗しても何も反応されない → でもトイレで成功したらめちゃくちゃ褒められる → 成功するようになる
つまり、犬にとって“良い行動”を強化するには、「成功体験」を重ねることが大切です。
叱られても「何がいけなかったか」が伝わらないことがほとんど。
逆に、「叱られる=怖い=この人が怖い」となり、信頼関係にヒビが入ってしまうこともあります。
■ 今どきのしつけは「ほめる・導く・整える」
しつけにおいて大切なのは、次の3つのバランスです。
① ほめる
→ 成功したときは大げさなくらい喜ぶ! 声・表情・おやつなどで「正解」を伝える。
② 導く
→ 「ダメ!」と否定するのではなく、「こっちが正解だよ」と導くように教える。
例)家具をかじる → 怒るのではなく、かじってOKなおもちゃを渡して褒める
③ 環境を整える
→ “失敗させない”環境づくりも大切。
例)トイレの場所を分かりやすくする、届いてほしくない物を片付ける、音に敏感な犬には静かな空間を用意する…など
■ トイレトレーニングの“あるある”
トイレのしつけは最初の関門。
特に子犬の場合は、「うちの子、全然トイレ覚えない!」と悩む方がとても多いです。
でも、よくある失敗パターンのほとんどが、「叱ってしまった」ことに起因しています。
たとえば…
失敗したときに「コラッ!」と大きな声で叱る
↓
犬は「排泄=怒られる」と思い込み
↓
見つからない場所(カーテン裏など)でこっそりするように…
これでは逆効果。
成功したときに「やったね!上手!」とほめる方が、犬にとってずっと分かりやすく学びやすいのです。
■ 家族全員で「しつけの方針」を合わせる
意外と見落としがちなのが、「家族でしつけ方がバラバラ問題」。
お父さんはソファに乗せるけど、お母さんはダメという
子どもは机の下でおやつをこっそりあげる
名前の呼び方が複数あって混乱…
こうなると、犬にとっては何が正解か分からず、ストレスや問題行動の原因になることも。
「ルールは家族全員で共有する」
これだけでも、犬にとっての安心度は格段に上がります。
■ しつけは“信頼関係”の上に成り立つ
何より大切なのは、犬が「この人のそばにいれば大丈夫」と思える関係性です。
声をかければしっぽを振る
名前を呼べば目を合わせる
何もなくても、近くで寝てくれる
そんな関係ができてくると、しつけもぐんと楽になります。
「お互いに伝えようとする気持ち」が、毎日の中で育っていくからです。
しつけとは、犬に我慢を教えることではありません。
犬と“気持ちよく暮らす方法”を、一緒に探していく旅のようなもの。
焦らず、怒らず、愛情をもって。
それが、いい関係をつくる最短ルートです。
【第四章】お金の話。意外とかかる?
「犬と暮らすって、そんなにお金かかるの?」
初めてペットを迎える方にとって、“費用面”は気になるポイントの一つですよね。
結論から言うと、犬との暮らしには想像以上に「毎月かかる出費」があります。
でも、正しく備えておけば慌てることはありません。
ここでは、初期費用から毎月のランニングコスト、意外な出費まで、現実的なお金の話を“正直に”お届けします。
■ まずは「初期費用」を確認しよう
犬を迎えるためには、最初にまとまった費用が必要です。
購入費や譲渡費用の他に、「暮らしの準備」が意外といろいろあります。
🛒 一例:子犬を迎える場合
- ケージ・サークル:1~2万円
- ベッド・ブランケット:2,000〜5,000円
- フードボウル・給水器:1,000〜3,000円
- トイレトレー・ペットシーツ:3,000〜5,000円
- 首輪・リード・ハーネス:2,000〜5,000円
- おもちゃ・歯みがきグッズなど:3,000円前後
- ワクチン接種・健康診断:5,000〜15,000円
- マイクロチップ装着(義務化):数千円
👉 合計で5万〜10万円程度を見ておくと安心です。
※保護犬の場合は譲渡費用が数千円〜3万円前後、ワクチン・避妊去勢手術が済んでいることもあります。
■ 「月々いくらかかる?」をざっくり把握
犬と暮らし始めてからは、食費やケア用品、医療費など、定期的にかかる費用が発生します。目安としては、月に1万円から2万円前後を見ておくと安心です。
具体的には、まず「フード代」が犬種によって異なります。小型犬であれば月に3,000〜5,000円程度、中型〜大型犬では食べる量が増えるぶん5,000〜10,000円程度と考えましょう。
そのほかに「おやつ」や「ペットシーツ」、「歯みがきグッズ」などの消耗品代が、月に1,000〜2,000円ほどかかることが多いです。
「ペット保険」に加入している場合は、掛け金として1,000〜3,000円程度(犬種・年齢によって変動)を見積もっておく必要があります。高齢になってからの加入が難しい保険もあるので、早めの検討がおすすめです。
さらに、「トリミング代」は犬種によって大きく差があります。たとえばトイプードルやシュナウザーなどは月1回5,000〜8,000円ほどかかりますが、柴犬や短毛種などはほとんどかからない場合もあります。
また、「動物病院の定期ケア(ワクチン、フィラリア・ノミ・ダニ予防など)」は、年間で1万〜2万円ほど。月に換算すると1,000円〜2,000円程度を見ておくと良いでしょう。
このように、日常的な出費は“ちょっとずつ”ですが、トータルすると想像以上に積み重なるもの。
「あとで慌てるより、最初から予算を組んでおく」ことが、犬も人も安心して暮らすポイントです。
■ 病気・ケガの「もしも」に備える
人間と違って、犬には公的な医療保険がありません。
そのため、動物病院での診療は「全額自己負担」となります。
たとえば…
- 軽い皮膚炎の診察+薬で:約5,000円〜
- 胃腸炎や骨折で検査+点滴+入院:約2万〜5万円
- 手術(異物誤飲・ヘルニアなど):5万円〜10万円以上
突然の高額出費に備えて、次のどちらかの対策があると安心です。
✔ ペット保険に入る
最近では「通院+入院+手術」に対応した保険プランが多数あります。
月々の掛け金は犬種・年齢により異なりますが、小型犬で1,000〜2,000円程度が相場。
※ただし、全額補償ではなく「50%補償」や「年間限度額あり」のものが多いので、内容は要確認。
✔ 医療費積立をする
ペット保険に入らず、月々5,000円ずつ「いざという時のため口座」に貯めておくのも一つの方法。
犬の年齢・体調に合わせて、柔軟に使えるのがメリットです。
■ 意外と見落としがちな費用あれこれ
犬との暮らしでは、思わぬところに出費が発生することも。
💡 旅行・帰省時のペットホテル代
1泊あたり3,000円〜5,000円程度が目安。長期旅行なら数万円に。
→ ペット可の宿を選ぶ、ペットシッターを活用するなどの選択肢も◎
💡 狂犬病予防接種・登録費用(年1回)
狂犬病予防注射:約3,000円
市町村への登録・更新料:年数百円〜1,000円ほど
💡 シニア期の介護用品・通院
高齢になるとおむつ代や介護マット、定期的な診察費などが増えます。
■ 節約と“賢い選択”のコツ
- まとめ買いや定期便を活用(Amazon、楽天など)
- 安価すぎるフードは注意(品質・安全性をチェック)
- トリミングが不要な犬種を選ぶと長期的には経済的
- ペットOKの賃貸を選ぶ際は敷金・退去費用にも注意
「お金のことを理由に、犬の健康や安全を妥協しない」
そのためにも、暮らしの中で“無理なく続けられる”予算計画を立てておくことがとても大切です。
【第五章】犬との暮らしで、心から大切だと思うこと
犬との暮らしは、時間とお金がかかります。
けれど、それらを遥かに上回る“豊かさ”と“幸せ”が、毎日のなかにたくさん散りばめられています。
それは、派手な感動ではありません。ドラマチックな出来事がなくても、何気ない日常の中にふっと現れる、そんなあたたかさです。
■ 「いつも通り」が、どれほどありがたいか
朝、目が覚めたら足元に丸まっている。
リビングで新聞を読んでいると、あくびをしながら隣に座ってくる。
仕事から帰ってきたら、しっぽを振って出迎えてくれる。
それだけで、「今日もいい日だったな」と思えてしまうんです。
犬は、ただ“そばにいる”だけで、家の空気をやわらかくしてくれます。
家族がケンカをしているときは不安そうに見つめ、誰かが泣いていれば、静かに寄り添う。
そういう感情の機微を、言葉がなくても敏感に感じとってくれる存在です。
■ 犬は「行動と言葉の一致」で愛を感じている
犬は人の言葉を理解している――そう思っている方も多いですが、正確には「言葉の調子や行動から感情を感じとっている」といわれています。
「かわいいね」と言いながら不機嫌な顔をしていれば、不安になりますし、
何も言わなくてもニコッと笑いながらなでれば、うれしくてお腹を見せてくれます。
大切なのは、「この人は自分に優しい」「ここにいて安心だ」と感じてもらえる日々の積み重ね。声のトーン、表情、手の動き…犬はぜんぶ見ています。
「ちゃんと伝えよう」とすることが、いちばんのしつけであり、愛情表現でもあるのです。
■ 家族に“役割”をくれる存在
犬と暮らしていると、ふとした瞬間に「自分が頼られている」と感じることがあります。
たとえば、散歩を楽しみに待っている目。
寝る前に必ず膝に乗ってくる習慣。
具合が悪いときに、そばから離れない姿。
そのたびに、自分が誰かの「必要とされる存在」なのだと実感させてくれるのです。
特に、子どもや高齢の方にとって、犬は“家族の一員”というだけでなく、
「自分の出番がある」「毎日のルーティンができる」という、生きがいの一部になることもあります。
■ 最後まで寄り添う覚悟と、かけがえのない日々
犬の寿命は、10年〜15年ほど。
人間よりもずっと早く年をとり、別れの時も必ずやってきます。
それでも犬は、後悔しないように生きています。
「明日も一緒にいられる」とは思っていない。だからこそ、今日を精一杯楽しもうとする。
飼い主の帰りを毎日楽しみにして、
「今」が幸せならそれでいい、と無邪気にしっぽを振る。
そんな姿から、人は多くのことを学びます。
「今を大切に生きること」
「小さな喜びを見つけること」
「黙ってそばにいる強さ」
そして、「ありがとう」と言いたくなる毎日をくれる存在。
それが、犬なんだと思います。
“うちの子”と暮らす覚悟と、たくさんの喜びを
犬との暮らしは、たしかに手がかかります。
トイレの失敗もあるし、深夜に吐いたり、いたずらでお気に入りの家具がボロボロになったりもします。
けれど、それを補って余りあるほどの笑顔と、安心と、あたたかさがあります。
犬は、人間に「ただそばにいる幸せ」を教えてくれます。
そして、今日を大切に生きることの大切さを、毎日そっと伝えてくれるのです。
“うちの子”との暮らしは、「犬を飼う」というより、「犬と生きる」こと。
一緒に笑って、時には泣いて、心を通わせながら日々を重ねていく――
そんな時間を、ぜひ味わってみてください。
今回は思わず長くなりました。