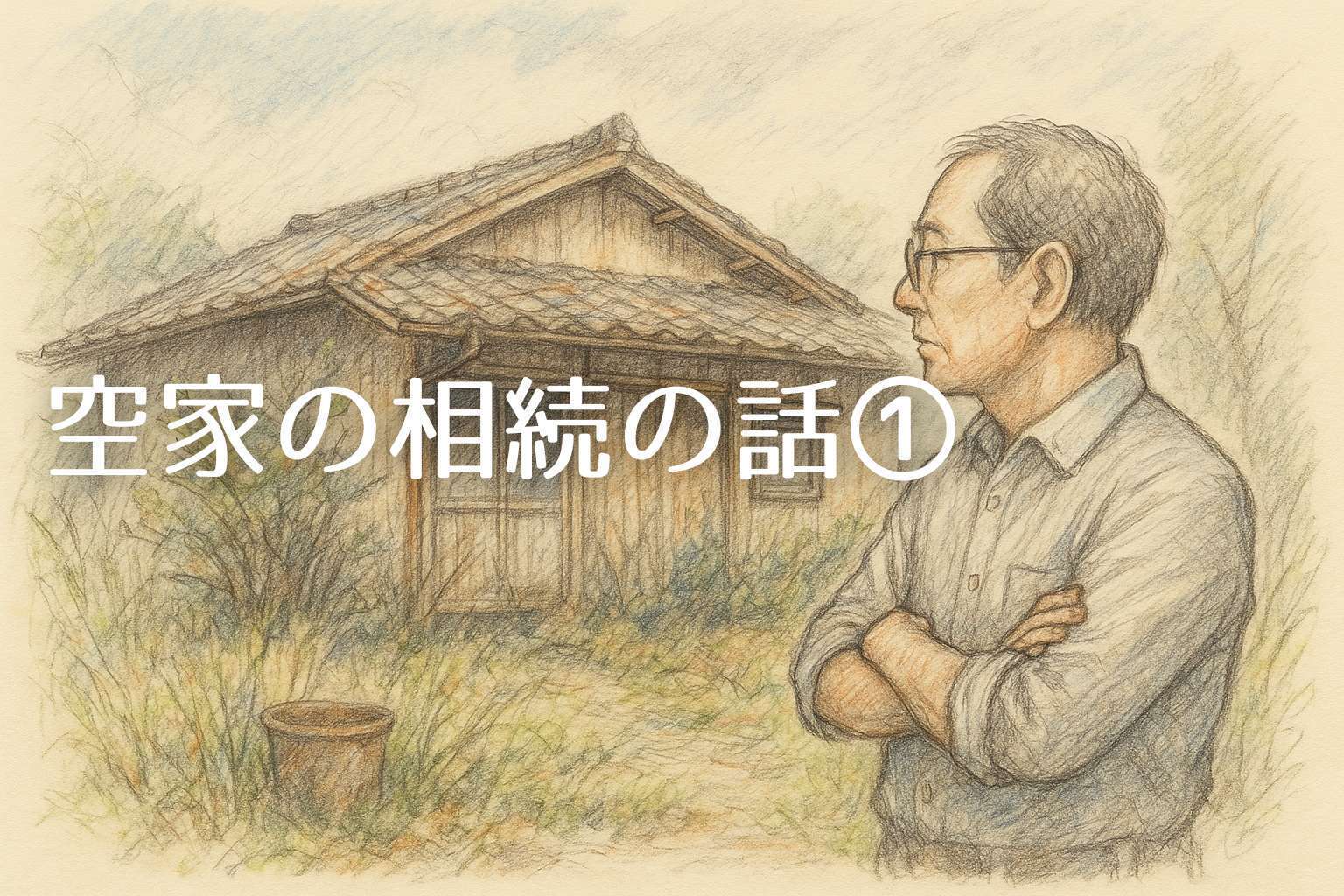名義が祖父のままの家を前に立ちすくむ太郎さんの話──相続登記をしないと動かせない家
誰も住まなくなった家、誰も動かせない家
「そろそろ、あの家をなんとかしないとね。」
夏草の匂いが濃くなり始めたある日、太郎さん(58歳)は古い実家の前で腕を組んでいました。
そこは祖父の代から受け継がれた木造の平屋。父が亡くなって十数年、もう誰も住んでいません。
屋根の板金は浮き、トタンの隙間からスズメが出入りし、
庭の柿の木の根元には、かつて祖母が置いていた植木鉢がそのまま残っています。
通りを歩くご近所さんが、申し訳なさそうに「草がこっちまで伸びてますよ」と声をかけてくれました。
太郎さんは「ええ、そろそろ片づけようと思ってるんです」と答えながらも、胸の奥は少し重たくなります。
兄弟は三人。
次男の次郎さんは神戸で会社員、長女の花子さんは東京で暮らしています。
話し合いの結果、「解体して更地にしよう」という方向はすぐに決まりました。
しかし、実際に動こうとすると、目の前に一枚の大きな“壁”が立ちはだかったのです。
「祖父名義のままです」──登記簿に残る、時代の影
太郎さんが市役所を訪ねたとき、職員が登記簿を確認して驚いたように言いました。
「この建物、まだおじいさんの名義のままですね。」
太郎さんは一瞬きょとんとしました。
「父の代で名義が変わっていると思っていましたけど…」
職員はやさしい声で説明します。
「相続登記をされていないようです。名義を変えないと、補助金の申請や解体届出も出せないんですよ。」
思いがけない一言に、太郎さんは頭が真っ白になりました。
家を壊すにも、売るにも、直すにも──
“所有者”がはっきりしていなければ、何も始められない。
それが「登記」という仕組みの現実なのです。
登記ってそんなに大事?──「誰の家か」を決めるもの
私たちが「自分の家」と呼ぶ建物でも、
法律上の「所有者」は登記簿に記されている人で判断されます。
つまり、名義が故人のままでは、
その家の“持ち主”は法的に存在しない状態になってしまうのです。
そうなると。
- 解体工事の届出が出せない
- 業者と正式に契約できない
- 市や県の補助金を申請できない
- 倒壊・火災が起きても責任の所在が不明
家そのものはそこにあっても、「誰も動かせない家」になる。
これが空き家問題の根本にある現実です。
2024年から「相続登記」が義務化に
これまで多くの人が後回しにしてきた“相続登記”。
それが2024年4月から、義務化されました。
亡くなった方の不動産を相続した人は、
相続が発生してから3年以内に登記をしなければならず、
怠ると10万円以下の過料(罰金)対象になります。
つまり、「やってもやらなくてもいい手続き」ではなくなったのです。
しかし、現場では──
「いざやろうと思ったら、相続人が多すぎて進まない」
「誰が関係者か分からない」
という声が後を絶ちません。
太郎さん一家も、そのひとつでした。
太郎家の相続関係──“誰が相続人なのか”をたどる旅
太郎さんの祖父が亡くなった当時、相続人は
祖母、父、叔父、叔母の4人でした。
その後、祖母と父も亡くなり、
現在の相続関係は次のようになります。
- 父の子ども(太郎・次郎・花子)
- 叔父(またはその子=従兄弟たち)
- 叔母
つまり、相続登記の関係者は5〜6人。
もし叔父や叔母が亡くなっていれば、その子ども(従兄弟)まで含まれ、
関係者は10人を超えることも珍しくありません。
この全員が「印鑑証明付きの同意書」に押印しなければ登記は成立しません。
それぞれの住所も、生活もバラバラ。
連絡を取るだけでも時間がかかるのです。
相続人が増えるほど、時間も費用もふくらむ
司法書士に相続登記を依頼する場合、
費用は一般的に7〜15万円ほど。
しかし相続人が多い場合、戸籍の取り寄せや書類作成の手間が増えるため、
20万円を超えることもあります。
放っておいた年月がそのまま“複雑さ”となって返ってくる。。。
まさに、相続は時間との戦いです。
「解体だけ先に」は、実はできない
太郎さんは地元の工務店に相談しました。
「登記はあとで進めるとして、先に解体だけお願いできますか?」
担当者は首を横に振りました。
「建設リサイクル法の届出には、発注者=所有者の名前が必要なんです。
名義が故人のままだと、届出が受理されないんですよ。」
つまり、登記を直さない限り、工事届も補助申請も出せません。
業者としても、トラブルを避けるために契約できないのです。
補助金制度も「登記」が前提
丹波篠山市をはじめ、全国の多くの自治体では
「老朽危険空き家解体補助金」などの制度があります。
しかし、申請要件には必ずこう書かれています。
「申請者は、所有者または相続登記を完了した相続人であること。」
つまり、登記が古いままでは補助金の対象外。
「せっかく制度があっても使えない」という声が全国的に上がっています。
太郎さんも例外ではありませんでした。
「やっぱり、登記を済ませないと前に進まないんだなあ」と、
ため息をついたといいます。
司法書士の力を借りて──登記の第一歩を
相続登記を進めるには、司法書士の力が欠かせません。
専門家はまず、戸籍をすべて取り寄せて「誰が相続人か」を明確にします。
次に「相続関係説明図」と呼ばれる家系図を作成し、
全員の同意を得たうえで法務局へ申請します。
司法書士の先生が、祖父から曾祖父の時代までの戸籍を取り寄せてくれたとき、
太郎さんは思わず笑いました。
「この人、うちの先祖だったのか…。まるで家の歴史書ですね。」
登記の手続きはたしかに大変です。
でも、専門家の手にかかれば少しずつ形になります。
「やるか、やらないか」で悩む時間よりも、
「やる」と決めて動いた方が、確実に早く終わるのです。
家族の話し合い──感情と現実のバランス
太郎さん、次郎さん、花子さんの3人は、
オンラインで久しぶりに顔を合わせました。
太郎さん「もう、あの家は危ないと思う。解体して更地にしておきたい。」
花子さん「お父さんが残した家だから、寂しい気もするけど…しょうがないね。」
次郎さん「でも、費用はどうする? 全部でいくらくらい?」
見積りは約250万円。
登記費用を含めると、決して小さな金額ではありません。
けれど、誰もが心のどこかで分かっていました。
「このまま放っておけば、もっと大変になる」と。
「放置」ではなく「整理」へ
話し合いの末、3人は決断しました。
登記を済ませ、太郎さんの名義にまとめ、
補助金を活用して解体を進める。
母の仏壇は別の家へ移し、
庭の柿の木の枝を少しだけ残すことにしました。
「これが家族の“けじめ”かな」と、太郎さんは静かに言いました。
解体が終わったあと、
更地に立って風を感じた太郎さんは、
「ようやく肩の荷が下りた気がします」とつぶやきました。
“動かせる状態”を保つということ
この出来事を通して太郎さんが感じたのは、
家を守るというのは「建物を残す」ことだけではない、ということでした。
名義を整え、動かせる状態を保つことも、
未来の家族を守るための“住まいの手入れ”なのです。
古い家をどう扱うかという問題は、
感情・費用・法律が複雑に絡み合うテーマです。
けれど、どんなに複雑でも、
“手をつけなければ前に進まない”という点では共通しています。
「もし登記をせずに自分が亡くなっていたら」
登記が完了し、新しい登記簿を受け取ったとき。
太郎さんは、ふと、もし自分が登記をしないまま亡くなっていたら、と考えました。
「たぶん、うちの子どもたちは、もっと苦労してたと思う。
祖父の名義のまま、自分も登記をしていなかったら、
今度は“孫たちの代”まで相続関係が続いていたはずだ。」
司法書士の先生は笑いながら言いました。
「そうなんです。これを“数次相続”といって、登記を飛ばすたびに関係者が倍になります。
太郎さんが今、手をつけてくださったから、次の世代は助かりますよ。」
太郎さんは深くうなずきました。
「登記って、家の“未来のメンテナンス”なんですね。」
地域工務店にできること
私たちのような地域の工務店は、
「登記」や「法務」は専門ではありません。
けれど、「家族が話し合いを始めるきっかけ」をつくることはできます。
- 登記簿の取り方を一緒に確認する
- 司法書士を紹介する
- 解体・改修の見積りを出して将来像を描く
そうしたサポートの積み重ねが、
家族が“動き出せるタイミング”を後押しします。
“相続登記”はゴールではなくスタート
相続登記を済ませることで、ようやく家は「動かせる状態」になります。
それは終わりではなく、始まりです。
- 売ることもできる
- 壊すこともできる
- 改修して貸すこともできる
- 補助金も申請できる
登記を整えるというのは、
家を未来に残すための「選択肢を取り戻す行為」なのです。
未来へ──“家がなくなっても、つながりは残る”
解体の当日、
太郎さんは工事の立ち会いをしながら空を見上げました。
「おじいちゃんの家、立派だったなあ。」
となりで次郎さんが笑います。
「今度は孫が家を建てる番かもな。」
花子さんはスマホで写真を撮りながら、
「ちゃんと整理できて、よかったね」と言いました。
家はなくなっても、
家族のつながりと想いは残る。
そして、そのつながりを守るのも、
私たち“家をつくる側”の仕事のひとつなのだと、太郎さんは感じました。
エピローグ──「登記簿を一度、開いてみませんか?」
あなたの家の登記簿には、誰の名前が書かれていますか?
もし、それが何十年も前に亡くなった方の名前のままだとしたら、
その家は今、あなたを待っているのかもしれません。
「放置」ではなく「整理」へ。
“相続登記”という静かな一歩が、
家と家族の未来を守る第一歩になります。
☆☆この記事を読んだ方にはコチラもおすすめ☆☆